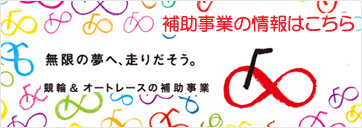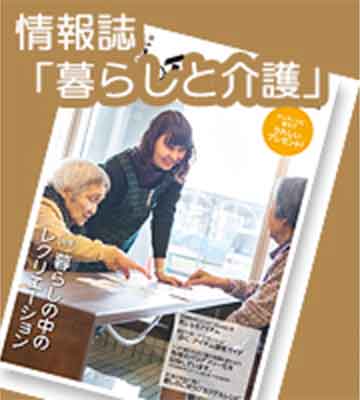医療従事者以外(例えばビジネスマン)でも必要なキャリア形成について
今年の4月18日に日本内科学会総会で「ことはじめ2025」というセッションにおいて、「内科学の素晴らしさ」、具体的には慶應大学病院の胃カメラのスペシャリスト(一つのことに特化して真似できない知識と技術を持つ人)の方と、私はジェネラリスト(物事について広く深い知識と経験をしている人)の立場として、ディベートを行う、ということになっています。内科学会に入会している人は現地(大阪)に行かなくても、後から配信されるようです(取り敢えず私は配信について承諾しています)。
私自身は自分のことを、どちらかといえばスペシャリスト的な開業医、と思っていたのですが、今回の講演依頼をうけて、熟考することができました。開業医はジェネラリストが向いている、が、スペシャリストがなれない訳ではない。医療(これをビジネスに置き換えてもいいのです)能力値の配分をどうするか、能力値そのものを上げる必要もある。そしてスペシャリストとジェネラリストの間には色のグラデーションのようなものがあり、自分がどのあたりにいるのか、ということをまずは知るべき、だということです。
また漫画「暗殺教室」でも語られていましたが、武器は1つで駄目で2つ以上の得意技を身につけるべし、ということもキャリア形成では必要だと、「ことはじめ」の打ち合わせでズーム会議した医師のほぼ全員が発言していました。私自身は心臓エコー検査を最も得意としているのですが、胃カメラや腹部エコーもします。また心臓エコー検査をするにあたり、開業医では絶対にしないけれども「カテーテル治療で人の命を救わない人がエコー検査だけをするのは、作成したエコーのレポートが弱い」と昔思っていたので(極限まで極めた人はそれには該当しない)、実はカテーテル治療も自身で責任をもってしつつ、集中治療室での全身管理のなか、エコー検査を学んでいました(同時進行でしていました)。
上記は私がキャリア形成という言葉を意識せずに行っていたことですが、今は時代も変わり、教える・教わるのが当然(医療においてはこれは必須だと思います)という風潮になっています。私の医療の信念として、多くの人の学びの場(患者さんにも)としてクリニックで医師として従事していきたいと思っています。
P.S)私も47歳になりました。ついこの前まで徳島の田舎で小学校の教諭であった祖母とサッカー、祖父と五目並べをしていた記憶があります。祖父は福田心臓消化器内科で誤嚥性肺炎で私が看取りました。看取った時の担当看護師の方が、私が医師1-3年目は往診なども一緒にしており、一緒に泣いてくれたのが救いでした。
そういった経緯もあり、誤嚥性肺炎を予防、また再発しないように、大学の同級生からも教えてもらいながら、自身でも医学書、論文を吟味して、福田心臓消化器内科で嚥下外来をしています。「口から今は食べることができない」「食事形態を変える、食事前にすべきこと」など説明できることもありますが、誤嚥性肺炎の予防に完璧なことは勉強していて困難だと思いつつ、より工夫をしていきたいと思っています。
一宮きずなクリニック
院長 福田 大和
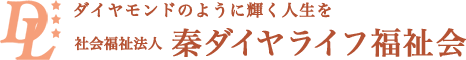
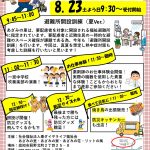


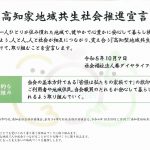


 あざみの里
あざみの里 絆の広場
絆の広場 あざみの家
あざみの家 三つ星日記
三つ星日記 あざみの荘
あざみの荘 ぼっちり横丁
ぼっちり横丁 風の大地
風の大地 ヘルパーステーションあざみ
ヘルパーステーションあざみ 馴染み横丁
馴染み横丁 リットの風
リットの風 誠和園
誠和園