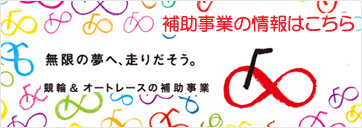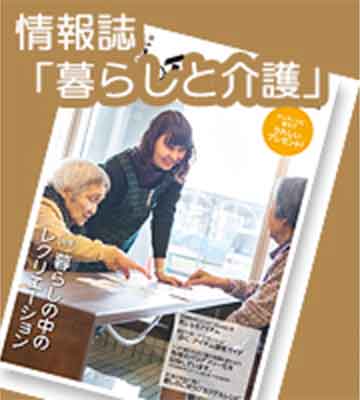- 介護保険の対象者
- 【第1号被保険者】65歳以上の方
- 【第2号被保険者】40歳から64歳までの医療保険に加入する方で、加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で、支援や介護が必要になった方
①相談します
地域高齢者支援センターや介護保険課で、利用したいサービスなどについて相談します。
②介護サービス認定の申請
※介護サービスを利用したい方
介護サービスを利用するには、要介護・要支援認定が必要です。
- 【申請先】
- 介護保険課
- 地域高齢者支援センター、出張所
- 窓口センター
- 【必要書類】
- 要介護・要支援認申請書
- 介護保険の保険証(65歳以上の人)
- 医療保険の保健証(40~64歳の人)
②基本チェックリストを受けます
※介護予防・生活支援サービスを利用したい方
地域高齢者支援センターで、心身や日常生活の状態など生活機能を調べる基本チャックリストを受けます。
- ○生活機能に低下がみられた場合
- 介護予防・生活支援サービスを利用できます。
- 【基本チェックリスト】
- ①杖をついたり、歩行器を使用しても一人で歩くことができない。
- ②認知症の悪化により日常生活に支障をきたしている。
- ③入浴や身体を洗うことが一人でできない。
- ④服薬や病気の管理のために訪問看護等の医療系サービスの利用希望がある。
- ⑤住宅改修や手すり等の設置、福祉用具のレンタルや購入を希望する。
- ⑥家族での介護が難しく、長時間の預かりを求めている。
以下の①~⑥に該当するものが1つ以上ありますか?
③認定調査を受けます
まず、心身の状態などを調べます。
- 【訪問調査】
- 介護認定調査員が自宅を訪問し、心身の状態を調べるため、
本人や家族などに話を伺います。
- 【主治医の意見書】
- 生活機能の低下の原因となった病気やけが、心身の状態などについて、
主治医に記載してもらいます。
次に判定・審査・認定を行います。
- 【一次判定(コンピュータ)】
- 調査結果をコンピュータで処理し、仮の要介護度を判定します。
- 【二次判定(介護認定審査会)】
- 保健、医療、福祉の専門家による会議です。一次判定結果、訪問調査、
意見書をもとに総合的に判断し、要介護度を認定します。
④認定結果が届きます
認定結果は郵送で届きます。
- 【認定結果通知書】
- 認定調査の結果が記載されています。
- 【負担割合証】
- 要介護度や認定の有効期間など、認定結果が追記されています。
次に判定・審査・認定を行います。
- 【負担割合証】
- 要支援・要介護と認定された人に送付され、介護サービス利用料の
負担割合が記載されています。
- 【二次判定(介護認定審査会)】
- 保健、医療、福祉の専門家による会議です。一次判定結果、訪問調査、
意見書をもとに総合的に判断し、要介護度を認定します。
【要支援1・2】
介護予防サービスや介護予防・生活支援
サービスを利用することで生活機能が
改善する可能性の高い人
【要介護1~5】
介護サービスを利用することで生活機能
の維持や改善をはかることが適切な人
⑤ケアプランを作ります
利用者の状況や希望をもとに、ケアマネジャーとケアプランを作成します。
- 【こんな時はケアマネジャーへ】
- 交通事故など第三者行為により介護サービスが必要になった場合、
利用料を介護保険が一時的に立て替えた後、加害者に請求します。
示談前にご連絡ください。
【要支援1・2】
○地域高齢者支援センターへ作成を依頼します。
【要介護1~5】
- ○在宅でサービスを利用する場合
- 居宅介護支援事業所へ作成を依頼します。
- ○施設への入所、入居を希望する場合
- 入所、入居する施設に直接申し込みます。
※特別養護老人ホームは要介護3~5の人が対象です。
⑥サービスを利用します
サービス事業所と契約し、ケアプランに基づいてサービスを利用します。
【要支援1・2】
○介護予防サービスを利用します。
(地域密着型サービスを含む)うる
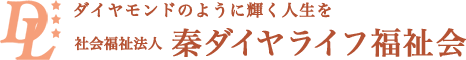

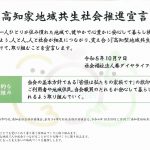


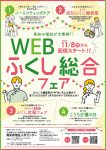

 あざみの里
あざみの里 絆の広場
絆の広場 あざみの家
あざみの家 三つ星日記
三つ星日記 あざみの荘
あざみの荘 ぼっちり横丁
ぼっちり横丁 風の大地
風の大地 ヘルパーステーションあざみ
ヘルパーステーションあざみ 馴染み横丁
馴染み横丁 リットの風
リットの風 誠和園
誠和園